保育実習生のみなさん、忙しい中お疲れ様です。
実習中は疲れてヘトヘトでも、帰宅後は毎日のように実習簿を記入しなければならないですよね。
文章が書くことに苦手意識があると、なおさらしんどく感じてしまうもの…。
でも、働きは初めてからも、保育日誌に個人記録表、指導案など、書き物も多いお仕事。
今から書くことに慣れておき、苦手意識を克服しておくと、働き始めてからもきっと気持ちが楽になりますよ!
今日は苦手な文章が苦手な人でも書けるようになる保育実習簿(幼稚園は「教育実習簿」)の書き方について、ポイントごとに整理してみたいと思います。
指導案(日案)の書き方のポイント②援助のポイントを考えよう
先生たちから好かれる保育実習生の心得14つ!学んで就職につなげよう
保育実習簿に書く内容
保育実習簿は、通っている学校から指定された紙で書いていきますが、園によって書き方が異なっている場合があります。
実習先の先生に聞き、まずは実習先の園に書き方を教えてもらいましょう。
丁寧に書く
実習簿は、丁寧な字で書き、担当保育者が読みやすいような字体にしてください。
書き間違わないように頑張っていても、書き間違えることもあるかと思います。
また、書いている内に、書きたいことが変わってしまった、などなど…。
実習簿を書き間違えた場合、訂正印を押すか、修正テープを使うか、紙を貼るかなど、実習先によって違うので、実習前に確認しておきましょう。
間違っても、「消せるボールペン」は使わないでください!!!
消せるボールペンは、実習簿を書くのにとっても便利に思えますよね。
でも、消せるボールペンは、暑いところに長時間置いておくと、消えてしまうこともあるので使わないようにしましょう。
メモは取っていいか確認する
メモを取ってはいけない、という園もあるので、先にメモを取ってもいいか聞いてみましょう。
活動の合間を見て、隙間時間にメモを取っておきましょう。
時系列もわかるように、大まかな時間も記入しておきましょう。
実習簿に書く内容
- 日付
- 天気
- クラス名と出席人数
- 担当保育士(教諭)の名前
- 実習の目標
- ねらい
- 活動内容
- 一日の流れ(時間・環境構成・子供の活動・保育者の動き・実習生の動き)
- 反省
学校や園によって様式は違いますが、このような内容になっているものが多いと思います。
日付・天気・クラス名と出席人数・担当保育士などは、そのまま記入していきましょう。
難しいのは、ねらい・内容・一日の流れの部分だと思いますので、この部分に焦点を当ててみましょう。
保育の「ねらい」と「活動内容」
実習簿に記入するのは、実習先の先生が行った保育に対する「ねらい」と「内容」です。
保育では、これまでの子供の姿に合わせて「ねらい」を設定し、ねらいが達成されるような「内容」を保育で行っていきます。
ねらい
保育における「ねらい」とは、子供たち成長を目指す目標地点のような物です。
「ねらい」を達成することによって、子供たちに何が身につくのか、どのように成長することができるのかを設定します。
「ねらい」は本来、子供の姿に合わせて設定するもので、その「ねらい」を達成するための保育の内容を決めていきます。
実習簿では、実習先の担当保育士が行った「活動内容」から「ねらい」を推測していく必要があり、作業が逆行する分、これは「どんなねらいがあったんだろう」と悩むものですね。
保育実習中はアンテナを張り巡らせておく
実習中に保育者が子供たちに掛けた言葉や援助の仕方からも、考察することができます。
保育実習中は、担当保育士がどんな「ねらい」をもって保育を行っているか、アンテナを張り巡らせておきましょう。
気になった声掛けや行動は、ひとまずメモを取っておきましょう。
わからない時は先に「一日の流れ」を書いてみる
「ねらい」は一番先に書くようにできていますよね。それは、本来は「ねらい」を設定した後に、活動内容を決めていくからです。
一番最初の「ねらい」がわからず立ち止まっていたら、先に進めなくなってしまいます。
分からない時は、先に「活動内容」や「一日の流れ」を書いてみてください。
書きながら今日の保育を振り返ることで、子供たちの姿を思い返し、「ねらい」を推測していく方がわかりやすい場合もありますよ。
POINT先に保育を振り返ってみて、その後に保育者がどんな「ねらい」を持っていたのか考えてみましょう。
担当保育士に聞いてみる
どうしてもわからず困っていても、まずは自分が考えた「ねらい」を記入して提出しましょう。
その上で、保育者に聞いてみると、いいと思います。
実習簿を添削する過程で教えてもらえることもあるし、「ねらい」が難しかったことを感想部分に書いておきましょう。
そうすれば、担当保育者が何かの形で教えてくれると思います。
また、直接聞いてみると、分かりやすく説明してもらえることもあります。
POINTわからないことは、とにかく聞いてみよう!
「ねらい」と「活動内容」の書き方
「ねらい」は、活動を通した具体的な目標を書きます。
例えば、砂遊びをした日について考えてみましょう。
「砂遊びを楽しむ」ことだけが「ねらい」ではありません。その先にある子供の成長した姿を捉えてみましょう。
砂が苦手で触りたがらない子供もいるかもしれません。
砂を触ったことがない子共もいるかもしれません。
そんな子供の姿から「砂の感触を十分に味わって砂遊びを楽しむ」ことや、「形が変わる砂遊びの楽しさに気付く」ことが、活動を通した子供の成長の目標となるでしょう。
「保育者と一緒に楽しむ」ことがねらいかもしれないし、「友達と協力して砂遊びをする」という部分がねらいかもしれません。
これだけではありませんが、年齢に応じた「ねらい」を考えて書きましょう。
そしてその「ねらい」の先に「活動内容」を書きましょう。
実習中は、活動を振り返って、具体的な「ねらい」が何であったかを考えてみましょう。
一日の流れ
一日の流れには、時間、環境構成、子供の活動、保育者の動き、実習生の動きがありますね。
時間は、実習簿では行われた時間を書きます。
環境構成
環境構成とは、保育者が事前に整えておくべき環境の部分を書きます。
保育者がどんな準備をしているか、また保育中にどんな風に環境を変えたのかを書きます。
保育では、「ねらい」を達成するための活動がスムーズに行えるよう、あらゆる準備をしたり、環境を整えたりします。
保育にとって「環境構成」はとっても重要な部分なのです。
環境構成は、例えば砂遊びでは「スコップやプリンカップを用意しておく」必要があるかもしれないし、「子供たちが好きなものを選びやすいように分類しておく」必要があるかもせれません。
砂の変化を楽しむために、途中で「バケツに水を入れる」という準備が必要になるかもしれません。
また、裸足で遊ぶのであれば、活動後に「足を洗うためのバケツ」を「洗いやすい場所」に置いておかなければなりません。
子供の動線を考えながら、具体的な環境を考えていきます。
実習簿では
実習では、保育者がどのように環境を準備していたかを書きましょう。
説明するのが難しい部分は、図にして書いてもいいですよ。
環境を勉強すると、いざ担任をもった時にとっても役に立つので、保育者の環境構成をしっかり勉強してみてくださいね。
書いているうちに、書き方がつかめるようになり、書き方がつかめたらある程度のパターン化された文章が出やすくなってきます。
子供の活動
子供の活動は、大きい見出しの下に、具体的な活動を書いていきます。
このように、砂遊びに対して、具体的に子供が行った活動を時系列で書きます。
保育者の動きと実習生の動き
担当保育者がどのような動きをしていたのか、また自分がどのように行動したのかを具体的に書きます。
保育者が、個々にかけた言葉や全体への指示なども、どんな援助をしていたのかも、分けて書くようにしましょう。
実習生の動きでは、子供とこんな風に遊んだ、こんな声掛けをしてみた、という子供への関わりの他に、机を出すなど、環境準備の手伝いなども書いていきます。
ここで重要なのは、保育用語をしっかりと使うことです。
初めて実習簿を書いている内は難しいのですが、援助を書く時には、ある程度決まった言葉があるので気を付けます。
〇子供の様子を見る ⇒ 見守る
〇応援する ⇒ 励ます
〇褒める ⇒ 認める
間違えないように書きましょう。
反省
反省では、今日の実習の目標に対してどう動いたか、どこが難しかったか、具体的に試してみたことを伝えましょう。
また、担当保育者の行動の中で、勉強になったことも書きましょう。
また、今日を振り返って、明日の目標を考えていきましょう。
その繰り返しが、保育の学びにつながりますよ!
自分の糧になると思って頑張ろう
実習簿を書くことは、PDCA(計画⇒実行⇒評価⇒改善)を行う一つの手段になります。
実習で具体的に何を学び、どのように行動したのかを記録し、フィードバックを通じて保育者として成長していくためのツールになるのです。
頑張って書いた実習簿は、仕事でも糧になるし、宝物になりますよ!
書く量が多くて辛い、と感じることもあると思いますが、その先にある保育者としての自分を想像して、頑張ってみてくださいね!
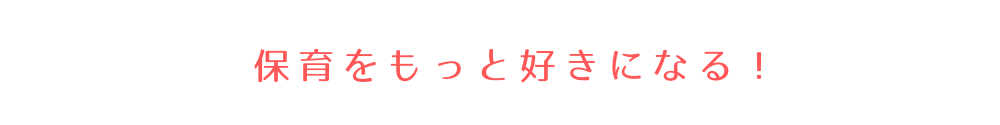





コメント