秋から年度末にかけて行われる事の多い作品展。
今までの制作活動の集大成として、様々に展示を行う事でしょう。
ただ、どんなテーマにしようか迷ってしまいますよね。
今回は、作品展で使えるテーマや、子供の表現を引き出すための展示を考えてみたいと思います。
共同作品制作のテーマ
クラスでテーマを決めて作ったり、園全体でテーマを決めて作ったりする共同作品製作についてご紹介します。
ぼくたちの保育園・幼稚園

園生活をテーマに、作品を作るもの。
大きな作品を作るクラスは、先生を作ってみたり、乳児さんでも簡単な給食の中身をを作ったりと、園生活をヒントに作品作りをします。
同じ園をテーマにしたものでも、様々なアレンジができて面白いですね!
園生活は子供たちにとって身近なもの。
イメージもしやすく、園全体として、テーマの一体感を強く感じられますよ。

年長組では、自分たちで話し合って、何を作りたいか考えたり、何を使って作りたいかなど、話し合う時間を設けてみるといいですね。
商店街へようこそ

〇〇幼稚園商店街などとテーマを統一し、クラスごとにお店を作ります。
保育室ごとにお店を作ってもいいし、遊戯室全体を街に見立て、お店を作って作品を展示するのもいいですね。
年長クラスは、最後に大きな地図を書いてもいいでしょう。
また、乳児さんでも簡単な食べ物製作で楽しむことができますよ。

商店街がテーマであれば、作品展後もお店やさんごっこをして遊ぶ事ができますね。
オリンピックなどの行事

オリンピックやワールドカップなど、大きな行事があった年は、その行事をテーマにしてみると面白いですよ!
オリンピックであれば、体操やマラソンなど、競技ごとに様々な展示をする事ができますね!
大きな作品を作っても、とても見応えがありますよ~!

開催された街についても同時に調べたりして、その国の様子も展示できるといいですね!
絵本の世界

子供たちが日ごろから親しんでいる絵本の世界を表現するのも、定番ですが楽しいですね!
クラスごとに絵本を変えてもいいし、遊戯室でひとつの絵本の世界を作っても楽しいです。
年齢によって読んでいる絵本は違うので、別々の絵本でクラスごとに決めてもいいですが、全体集会などで定番の絵本があるのであれば、その絵本を使うことで、どの年齢のクラスでも同じテーマで作ることができますね。

クラスごとに絵本を変えて、そのまま劇遊びや生活発表会につなげていくこともできますよ!
おもちゃの世界

子供たちの保育室にあるおもちゃを、大型作品にしても楽しいですね!
ブロックやままごと、レゴなども面白いですね!
いつも遊んでいる子供たちだからこそ、おもちゃの特徴も捉えやすく、また子供ならではの視点で作品制作が進められますよ。
おもちゃも、子供たちにとっては身近であり、イメージがしやすいですね!

おもちゃの世界でも、作品展後に作品を使って遊ぶことができますね!
キャラクター系
アンパンマンやディズニー、ジブリなど、キャラクターものが使えるのであれば、作品展のテーマにも使えますね!
子供たちが大好きなキャラクターなら、制作活動も積極的に行ってくれますよ。
個人作品制作のテーマ
個人作品制作は、共同作品制作と同じテーマで作ってもいいし、個人作品制作のみのテーマで作ってもいいですね。
今回は、個人作品制作に絞って考えていきましょう。
海・山などの自然

”海の世界”や”山の世界”など、自然をテーマに個人作品を制作します。
ありきたりなテーマですが、子供も身近に感じられる物が多いと思います。
また、テーマを幅広く取っておくことで、子供が自分で作りたいものを選択しやすくなります。
生き物の世界
自然と同じようなテーマですが、”水族館”や”動物園”などの方法もありますよ!
例えば、遠足で水族館に出かけたのであれば、水族館をテーマにしやすくなります。
将来の夢

年中から年長にオススメなのが、将来の夢を叶えている自分を作ること。
将来の夢も、年少まではイメージがつきにくい子供もいますが、年中さんくらいからは、職業としての夢を考えられるようになります。
「ヒーローになる!」という夢でなく、あくまで職業で考えることで、仕事についての興味や関心も引き出すことができますね。
絵画は年度初めから取り組む
作品展があるから、と秋に描いた絵画だけを展示するのでは、子供の成長の様子も見られません。
年度初めから少しずつ取り組むことで、絵画にも慣れてくるし、作品ごとに子供の成長が見られます。
また、作品展で展示する絵画も、同じテーマばかりにならないようにします。
など、様々な分野から、色々な素材を使った作品を並べると、楽しい作品展になりますね!
教材の研究を大切に
絵画は、保育者の教材の研究が大切です。
準備が大変ですが、教材をよく知ることで、作品のアイデアが広がります。
絵の具では、溶く水の濃さによってイメージが変わるし、混ぜる色の分量によってイメージとは違う印象の色になってしまいます。
ペンが思ったよりうまくにじまなかったり、パスの筆圧が弱すぎて色が出ないという事も。
年齢にあった技法で、一つ一つ丁寧に教材を準備することが大切です。

私は絵画が苦手だったので、教材の研究にもとても時間がかかりました…。
作品制作は環境を大切にしよう

作品展に関わらず、子供の制作を行う時は、事前の環境構成がとても重要になってきます。
年齢によって、使う材料を限定したり、なんでも使えるようにするなども、決めていくといいですね。
材料や廃材は素材ごとに選びやすく
子供たちが材料を選びやすいように、素材ごとに段ボール箱などに入れて、分類しておくことが大切です。
また、制作をする場所と材料を選ぶ場所の空間分けをし、子供の動線を考えて配置することで、子供たちがより材料を選びやすくなります。
図鑑などの本や写真を掲示しておく
絵本の世界の時はもちろんですが、テーマに関連するものや、作りたい作品に関連するものの写真や本を、コピーして壁に貼ったり、本は見やすい所に掲示しておき、子供たちが興味を持てるようにします。
また、製作途中でも、調べたいと思ったことを、子供たちが自分で調べられるような環境を整えることで、子供たち自身のイメージに作品を近づけることができますよ!
低年齢児は保育者と一緒にする楽しさを
低年齢児は、特に保育者の準備や教材の研究によって、作品が決まってきます。
子供たちは、作品の出来そのものより、保育者と一緒に制作をする楽しさを味わったり、自分が行った作業がこんな作品になるんだという発見を大切にしていくことが大切です。
ぬたくりや、パスでの自由画など、子供がのびのびと楽しめる表現を大切にしましょう。
展示方法のアイデア

作品展はあくまで子供の作品が主体
作品展でありがちな失敗は、作品そのもののクオリティーにこだわり過ぎたり、作品の展示方法にこだわり過ぎたりして、子供の作品が活きてこない事です。
パッと目を引くような大胆な飾り付けもインパクトがあり、保護者からの評判はいいのですが、大切なのは子供の作品であり、子供の作品をどう映えさせるか、という展示をする事です。
部屋全体を使って詰め込みすぎない展示をする
テーマの世界観を出すために、子供の作品より大きな飾りを作ったり、作品数が多すぎてゴチャゴチャになってしまうと、子供の作品が映えません。
かと言って、ただ子供の作品を並べただけの質素な展示も、テーマを元に作ってきた子供の作品が、印象が弱くなってしまいます。
壁は大きな布を張るなどして生活感をなくすだけでも、作品が目につきやすくなります。
テーマに合った色の布を、事前にたくさん用意しておくと、飾りつけがスムーズに行えますよ。
また、机やいすを積み重ねて段差を作り、テーマに沿った雰囲気(例えば船に見立てるなど)を出すことで、作品が見やすく、見ている側のイメージも付きやすくなりますね。
また、作品数が多すぎると、一見すると目を引く印象ですが、一つ一つの作品は見にくくなりがちです。
部屋全体に、コーナーごとに作品を並べるなどして、子供の作品が見やすい展示を心がけましょう。
製作過程を掲示する
見に来た保護者は、作品そのものは見ることができますが、園でどのようにして制作に取り組んだかを見ることはできません。
大切なのは、作品の制作過程での子供の成長であり、保護者にこんな風に頑張ったんだよ、こんな所の工夫ができるようになったんだよ、という事を見てもらいたいですね。
また、保護者としても、先生がこんな事を大切に取り組んできたんだというのがわかると、より作品を見るのが楽しみになりますよ。
模造紙に、制作過程を写真付きで掲示することで、保護者にも伝わる作品展になると思います。
子供たちのありのままの姿を写真に撮り、飾ってあげてくださいね。
子供たちの笑顔を引き出す作品展に☆
子供たちのその年齢での1年は、一生に一度です。
決して背伸びせず、ありのままの作品制作を心がけてくださいね!
子供たちが伸び伸びと表現できている作品展は、子供の素直な笑顔が引き出せれること間違いなし!
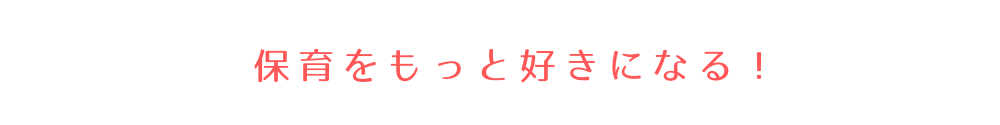




コメント